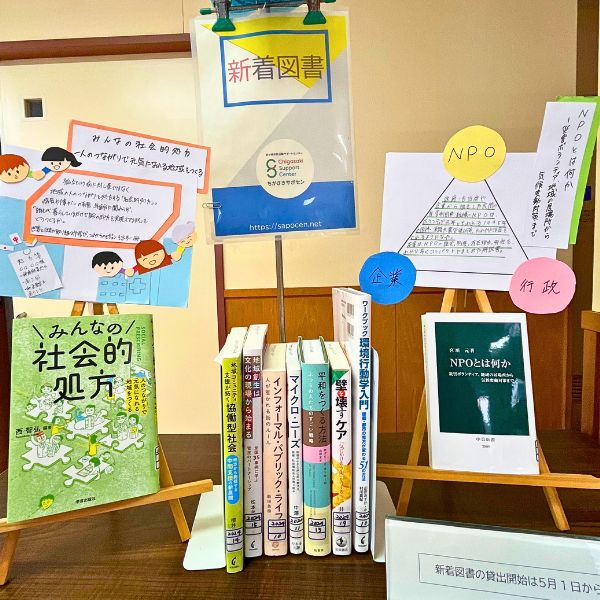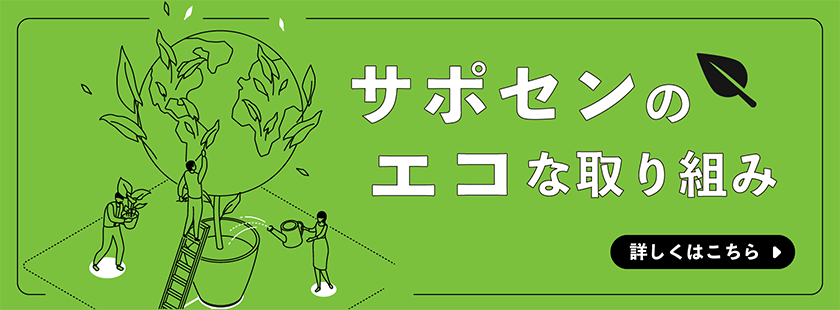【オススメ図書】Vol.15「新着図書」のご紹介
ぜひ お手に取ってご覧ください!

孤立という病に対し薬ではなく地域の人のつながりを処方する「社会的処方」。日本での実践はまだ始まったばかりだ。いま孤立しているかどうかや、病気や障がいの有無、年齢に関わらず、「誰もが暮らしているだけで自分の生き方を実現できるまち」をどうつくるか。世界と日本の取り組みに学び、これからのビジョンを示す一冊。

政府・自治体や企業から独立した民間の非営利団体・組織=NPO。阪神・淡路大震災後のボランティア活動以降、広く知られる。近年、子どもの貧困や孤独、気候変動など新たな社会課題が顕在化すると、行動の中心となり、活動分野と範囲を拡大。かつての会社や地域社会のような人と人を結び付ける「中間集団」が細るなか、その受け皿としても注目される。本書は、歴史、制度、存在理由から特性まで、把握しづらい実態を描く。

東日本大震災やコロナ禍、そして高齢化・人口減少の現実を前に、地域コミュニティは様々な課題に直面している。そうした中、地域円卓会議やアウトリーチ型支援等を通じて地域コミュニティをエンパワメントする中間支援組織の実践が各地で広がっている。こうした中間支援機能の事例をもとに検証し、新たな可能性を展望する。

実践者の感性・感覚で取り組まれてきた暮らしのためのまちづくりに、強い足場を提供してくれる「21世紀のまちづくりのバイブル」となる一冊。著者のニュータウンでの暮らしで感じた”暮らしにくさ”から始まる、その暮らしにくさがどこから来るのかを解き明かし、暮らしやすさを自分たち自身の手で生み出せることを伝えてくれる、日々の暮らしの中の疑問に答える一冊。

「文化の現場」は従来の文化施設だけでなく、観光・産業振興、地域活性化・まちづくりなど地域のあらゆる分野に広がり、地方自治体における文化政策をめぐる状況は激変している。全国の現場を歩いてきた著者が、歴史・環境・食文化などの視点から、人材や官民協働のあり方に焦点を当て、よりすぐりの35事例を紹介。

高齢者介護、児童福祉、障がい者福祉、外国人支援など、近年、医療や社会福祉に求められるニーズは多様化している。こうした中、著者は、医療法人・社会福祉法人の代表として、マイクロ・ニーズに応える実践を編み出し続けている。

ケアは福祉の専売特許ではない! 当たり前に「ケアしあえる街」を取り戻そうと、地域に根を張り、人と人とをつないだ「創造的壊し屋」たちがいた。本書は、ケアの常識に敢然と立ち向かう九人の実践家の奮闘記。

コロンビア、ソマリア、イスラエル、パレスチナなど、世界12の紛争地域で、20年以上にわたり調査を行ってきた著者が、暴力を止めて平和をつくる新たなアプローチについて、自らの経験をもとに解説する。

思わず腰を下ろしたくなる場所など、利用者の行動に影響を与える興味深い空間がある。このような場所と行動を観察することで、設計者は「ほどよい空間」をつくることができる。都市に暮らす人びとの生態をつぶさに観察する環境行動学の調査手法を、ワークブックの形式で学ぶ一冊。
★ 図書貸出希望の方は窓口まで!(一人3冊/2週間、新着図書は一人1冊まで)
★ 図書一覧はコチラから
▼Vol.14 Vol.13 Vol.12 Vol.11 Vol.10 Vol.9 Vol.8 Vol.7 Vol.6 Vol.5 Vol.4 Vol.3 Vol.2 Vol.1