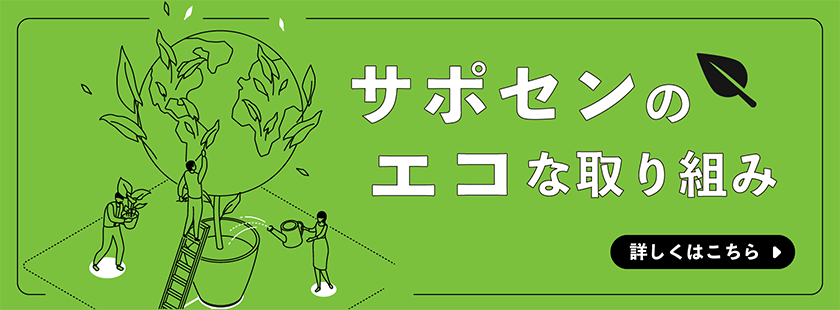【開催報告】1/26(日) SDGsカフェ12「農がなければ食もなし 〜地域から考える都市農業の未来~」
♦日 時:1月26日(日) 14:00~16:00 ♦参加者:37名
♦会 場:ちがさき市民活動サポートセンター フリースペース大
♦プログラム
① ゲストスピーカーによる事例報告
・石井 雅俊さん(NPO法人ふるさとファーマーズ 代表)
・酒井 彩子さん(オーガニッカーちがさき 代表)
・吉野 正人さん(茅ヶ崎どっこいファーム 園主/オーガニッカーちがさき コアメンバー)
② クロストーク
ふるさとファーマーズ ✖ オーガニッカーちがさき
③ グループワーク
④ 全体会
ワークまとめの共有・ゲストスピーカーからのコメント
ゲストスピーカーによる事例報告
石井 雅俊さん
(NPO法人ふるさとファーマーズ 代表)
ふるさとファーマーズでは「環境にやさしい野菜づくり」をテーマに、“小学校の出張授業” や “まいばすけっと労働組合さん(イオン系列スーパーマーケット)” など、企業の従業員に対する研修会講師などの活動を行なっています。
以前わたしは、不動産会社で農地の宅地化などの業務を担当していたのですが、コロナ禍の時に転機が訪れました。コロナ禍がずっと続けばいずれ日本は食料を輸入できなくなる、そう思っていた時に農家さんと出会い、自分でも畑作業をするようになりました。当時は川崎市にいたのですが、その後茅ケ崎里山公園にご縁をいただき、5年前から茅ヶ崎市で「みんなが参加できる畑」をスタートしました。活動を続ける中で昨年NPO法人格をとりました。
現在、農業・食料生産に関わる産業が、世界の温室効果ガスの3分の1を排出しているというデータがあります。またこのままでは、2050年までに4千万人が土地から追い出され、10億人が土壌の砂漠化により難民になると推計されています。これは、農薬や化学肥料による農業の工業化で土壌が痩せていくことが原因のひとつと言われています。気候変動に無関心でいられる人はいても、無関係でいられる人は誰一人いないということです。気候変動・フードロス・少子高齢化の中で、農のあり方を見直していかねばならない。そして、まずは地球環境を再生させることが大切なのではないかと思い、僕たちはこの活動をしています。そうした中で、不耕起栽培は環境再生型有機農業と言われています。耕さないことで土壌からの二酸化炭素の排出を抑え、炭素の貯留ができるということです。また、生物多様性の回復にも役立ちます。僕たちの畑でも準絶滅危惧種の虫が数多く暮らしていて、以前土壌の微生物量や炭素固定量などを調べた際に、たくさんの微生物が生息していることがわかりました。このように、不耕起栽培は気候変動問題の解決策の1つとも言われています。
「本当にこのままでいいのか?」という問いを、より多くの人に投げかけたいという想いから、学校でお話をさせていただいています。不耕起栽培の可能性や農業の大切さについて、これまでに13校を訪問し、30回ほど授業をさせていただきました。そして、香川小学校と茅ヶ崎小学校では、子どもと一緒に畑づくりをしています。そこで、去年、子ども達と一緒に大豆作りをし、収穫まで行きました。その結果、面白いことが起こったのです。子どもたちが学校で、大豆バスケット(フルーツバスケットの大豆バージョン)という新しい遊びを作っていました。チームに分かれて大豆バスケットをしたり、大豆のクイズをしたり。3年生に進級した子どもが、2年生に大豆畑を守って欲しいと、プレゼンをすることもありました。茅ヶ崎小学校は、ふるさとファーマーズの畑へ遠足に来てくれました。
また、タウンニュース社が運営する「うみかぜテラス」と一緒に、不耕起栽培講座を全4回開催しました。ふるさとファーマーズの学生バージョンで、ジュニアファーマーズという団体があるのですが、彼女たちは、不耕起栽培に関して同世代に SNSで発信したり、新聞を作ったりしています。
企業とのコラボレーションについては、イオンリテールワーカーズユニオン、まいばすけっと労働組合、ドクターブロナーなど、たくさんの企業の方にも畑に来ていただきました。REGENERATIVE ORGANIC認証(環境再生型有機農業)をしているのが、アメリカのパタゴニアとドクターブロナーなのですが、そのドクターブロナーがふるさとファーマーズの畑に来て、イベントを開催してくれました。企業も少しずつ変化をしているという実感があります。
最近は、ふるさとファーマーズの活動がメディアで掲載されることも増え、「農」に対する関心の高まりを感じています。やはり「食べることは生きることだ」と、僕は思っています。どんな農法であれ、地球という土台がなければ、おいしい食卓も成長する経済もありません。この気候変動が続いていくと、60年で土壌は完全砂漠化してしまうとも言われています。今、環境再生をすることが重要だと考えています。しかし「正しさ」で押し通すのではなくて、楽しいとか美味しいとか、そういったことが人を惹きつけるのだと思うので、今後もそうしたことを意識しながら、僕たちは「農」に取り組んでいきたいと思っています。
〇 〇 〇
酒井 彩子さん
(オーガニッカーちがさき 代表)
オーガニッカーちがさきの発足は、2023年の3月1日。元々食育を学び発信していましたが、ある映画との出会いがキッカケで、この活動を始めました。現在コアメンバーは8名。グループLINEに登録されているメンバーが80名以上(現在は92名)。オーガニッカーちがさきのコンセプト(理念)は、自然・人・食。オーガニックな繋がりと暮らしを考え、支え合い楽しむ。そんな「想い」を共有する仲間たちの集まりです。発足のキッカケは、2023年の2月に「食の安全を守る人々」という映画の上映会で、これを作られた山田正彦先生と出会ったことです。先生が日本全国を回ってこういう活動をされているのを知り、地元の茅ヶ崎ような農家さん、学校関係者とともに、オーガニッカーちがさきを発足しました。
団体の活動には、四つの柱があります。
一つ目は、オーガニック農家さんと市民を繋ぐということです。
オーガニック食品を食べたいと思っても、どこに行ったら買えるのか分からない方達もいるので、オーガニック野菜農家リストを作成して、市民の皆さんと農家をつなぐということをしています。具体的には、農家さんのイベント情報の提供です。 マルシェに出店する農家さんも多いですが、どのマルシェにどこの農家が野菜を出品しているかについての情報を共有させていただいています。また、野菜販売会のサポートとして、市役所前の広場で開催されるバザーに出店したり、若松町の「夢ある街のたいやき屋さん」前のデッキで販売をしたこともありました。さらに、援農という形でオーガニック農家さんの畑で種をまいたり、雑草を取ったり、収穫などの体験をしながら手伝う機会を共有しています。
二つ目は、オーガニック農家さんとレストランをつなぐ活動です。
オーガニック野菜をお店で使っていただくとか、お店に野菜を置いていただくとか、販売をしてくださるレストランが市内に何件かあります。
三つ目は、オーガニック農家さんと学校をつなぐ活動です。
学校給食にオーガニック野菜を使って欲しいという思いがあります。2023年7月から現在までに6回、人参・じゃがいも・大根・里芋などのオーガニック野菜を、学校給食に納入しました。吉野さんの「どっこいファーム」さんや小沢農園さんなどが精力的に関わってくださって、納入が可能になりました。 地産地消で、配達のコストもかからないし、栄養価の高いものを子どもたちが食べることができます。また、学校に出向き、学校での菜園サポートもしています。緑が浜小学校では、ジャガイモの袋栽培、松林小学校ではヘチマの栽培が、吉野さんの力をお借りして実現しています。オーガニック野菜を学校に納品する時に、栄養士さんとの交流が生まれ始めました。その中で、自分の学校の子どもたちに畑を見せたいという声があり、実際に子どもたちを畑に連れてくる、畑体験サポートということもしています。2年前、松林小学校の皆さんがどっこいファームに来て、ニンニクの植付けと収穫をされました。昨年の12月には小和田小学校の皆さんが小沢農園に来て、玉ねぎの苗の植付けを体験しました。
四つ目は、上映会などのイベントの開催です。
8月31日に体験学習センターうみかぜテラスで「食べることは生きること」という映画を上映しました。この時は、来場者が200名以上で、あっという間に受付けが締め切りになりました。映画の中で、アリス・ウォータースさんは何度も「ファーマーズ・ファースト」の言葉を使っていました。「農家さんが一番だ」ということ。農家さんの作ってくれた野菜を、そのまま食卓に運ぼうという活動が「ファーム・トゥー・テーブル」というのですが、映画上映会当日、実際に交流会を設けました。MOKICHI FOODSGARDEN(モキチ・フーズガーデン)のご協力により、オーガニック農家さんの野菜を、そのままレストランに持ち込みシェフに料理していただき、その料理を食べながら交流会を開催することができました。この上映会を企画するキッカケは、私たちが二宮町でアリス・ウォータースの映画上映会を見たことでした。二宮町の500人のホールが満席になるほど人が集まっていたことに刺激を受け、茅ヶ崎で上映会をしたいと思ったのでした。湘南エリアでは、逗子・藤沢・葉山・海老名などで上映会が開催されています。この映画の上映会がきっかけとなり、上映会の主催者同士の横の繋がりができています。
今後のオーガニッカーちがさきの抱負です。まずは、自然発生的な皆さんとの繋がりの中から、環境に負荷をかけない循環型農業を応援すること。家庭や学校給食の地産地消率をアップすること。 そして、農業体験を通して子どもたちへの食育を推進し、持続可能な環境や食の安全を広めていくことで、お役に立てればよいと思っています。
〇 〇 〇
吉野 正人さん
(茅ヶ崎どっこいファーム 園主/オーガニッカーちがさき コアメンバー)
今日は農家として来ているので、その立場からコメントをさせていただければと思います。先ほど、石井さんが小学生向けに制作した動画の中で、「有機農家はウンチを使っている」というシーンがありましたが、私のところでは使っていません。使うのが嫌だからというより、使わなくてもいい方法をとっているからです。小学生に「有機農業はどんな感じ」と聞いたとき、汚いとか臭いということになると、将来嫌われるんじゃないか・・・と。また、不耕起栽培の説明がありましたが、“耕さない農業” は農家の中で普通にやっています。ここは耕さないでいい、というところはできるだけ土をいじらない。だから慣行農業という、戦後普及した言葉はここ何10年間のことで、それまでは普通の農家さんが、みんなオーガニック農家だったのです。当時は、農薬もトラクターもなかったのですから。
今年は戦後80年。戦争が終わって使い切れなくなった毒ガスなどを農薬に変えた、殺虫剤もできた、肥料もできた。そうして、爆発的な生産高を誇るようになって、我々は生き延びてきました。だから、そういう農業技術の発展がなければ、我々は到底生き延びられなかった。この国の一つの現状としては、農薬や肥料がどのぐらい安全なのか、食の安全について、一般市民の関心がすごく高まってきている。今使われている農薬・肥料は、全て国が認証しているものです。ところが、こういう現状があるのです。ヨーロッパで締め出されて使用禁止とされているものが、日本のホームセンターで普通に売られています。同じこの世界の中にいて、そんな基準がバラバラでいいのかということになる。こういうコメントをする人もいるので、結局は、自分で決めるしかないのです。そうなると「自分で作りましょう」という話になります。私は、家庭菜園出身で、20年ぐらいやってから、定年が近づいたので農家になってみようということで、改めてオーガニックの勉強をしたのです。自分で作る体験や人が作っているところを見る、土に触れてみる体験をお勧めします。自分で育てた野菜を手にした時に値段をつけることすらもったいなくてできない、というくらい愛着が湧くでしょう。
どんな方法でもいいので、まず自分で作ってみるところから始めるとよいと思います。農家にもいろんなスタイルがあります。私は、色々な受け入れ体験をして、自分も楽しむというスタイルを取っています。実は明日、松林小学校の3年生が150人、うちの畑に来るのです。人参を抜いたり、室(貯蔵所)に埋めてある里芋のひげとりをしてもらおうと考えています。子どもたちに、土から出た野菜がそのまま売られているのではなくて、農家の仕事は色々ある。野菜を育てるだけじゃなくて、買ってもらえるように掃除や色々なことをして、みんなが見ている野菜になるということを経験してもらいたいのです。学校にいつも話すのは「せっかく子どもが作ったのだか繋がりったのだから、給食室とコラボしようよ」と。ちょっと工夫すれば作れるということを、少しでも子どもたちに体験してもらいたいのです。
一般の方々が「農」というものと、どうしたら繋がり易くなるかを意識して活動しています。
クロストーク
NPO法人ふるさとファーマーズ ✖ オーガニッカーちがさき
(石井さん)吉野さんのお話は農家さんならでの目線で、ご指摘もその通りだと思いました。こうやって教えていただくことは、本当にありがたいことだと思います。慣行栽培の農家さんも含めて、まずはすべての農家さんに対して、僕たち消費者がリスペクトすることが大切だと思います。また「農」に関わる中で最近気になっているのは、学校給食です。給食は、子どもたちが実際に食べ、身体を作っていくものですから。子どもたちが何を食べているか、食物がどういう作られ方をしているかを、先生たちが知ることはすごく大事だと思うのです。学校での食育がもっと広がるためにはどうしたらいいかについて、お知恵を拝借したいです。
(酒井さん)私の食育セミナーを聞きに来る方は、もともと「食」に関心のある方たちです。だから、「食」にあまり関心がない人は、食育について学ぶ機会がないまま日々の生活を過ごすことになる。一方、学校給食はすべての子どもに関わることなのです。学校給食は行政も絡むし、個人の力でどうにかなるものではないと思い、関わらないようにしてきたのですが・・・「食の安全を守る人々」という映画を見た時に、韓国では学校給食は教育の一環として、オーガニック給食が広まっていることを知り、子どもには平等に安全な「食」が与られるべきだ、と思い直したのです。たまたま、オーガニッカーちがさきのメンバ繋いでーの中に、元学校教員の杉本さんがいたので、学校の栄養士さんに繋いでもらいました。
会を立ち上げた時には、学校給食はずっと先の目標と思っていたのですが、設立して半年くらい経った時に、吉野さんから「今年はジャガイモと人参ができすぎた」という話があり、学校に声かけてみることになったのです。市役所にお願いして全校同じようにしようとしたら、もっと時間がかかったのかもしれないのですけど、「地産地消の有機野菜です。今朝、抜いた野菜がそのまま学校に届く」とアピールしたら、賛同してくださる栄養士さんが手を挙げてくれました。もちろん発注のタイミングなど色々あるので、全員が賛同していたわけではないと思うのですが、こうして期せずして夢が叶いました。栄養士さん、調理師さん、そして学校の校長先生はじめ、教員の皆さんとの繋がりとコミュニケーションをとることが大切だと思います。例えば、栄養士さんに畑に来ていただくことも考えています。とは言え学校の先生たちは多忙で、なかなか時間をとっていただくのが難しいので、栄養士さん向けの研修会に携われたらいいと思っています。
(吉野さん)子どもたちは、自分が採った人参が給食に出た時にすごく喜ぶし、自慢すると思います。よく自分の畑に来る家族から「食べず嫌いだったものが食べられるようになった!」という話を聞きます。何故なら、自分で採ったから・・・というのは、とても大きいことだと思うのです。食は、全て命をいただくことだから。ビーガンの方が「命を奪うことはできない」と言うけれど、野菜も命です。もっと分かりやすく言えば、豚や牛や鳥、魚が血を流しながら、我々の食卓に上る。そいうことを一番身近で、しかも接する回数が多いのが野菜だと思います。そういう意味で、子どもたちに繋げていただく機会が多いのが、栄養教諭です。栄養教諭は全教科にわたって、食の大切さを子どもに繋げていく大切な役目をもっています。
(酒井さん)吉野さんは、いつも「農家にならなくてもいい。家庭菜園の延長でも学校農園でもいい。家庭自給率、学校自給率を上げたい」と言っています。学校で自分たちが作ったジャガイモが、肉ジャガで給食に出てきたら最高じゃないですか。ところで、学校の農園は砂地のところがあるでしょう。石井さんに「実際に学校の土地を畑化するのに、どんな苦労があり、どんな工夫をしているのか」をお尋ねします。
(石井さん)学校の土地は砂利のところが多く、結構苦労しています。ふるさとファーマーズでは、畑づくりをイベント化していて、子どもたちに「野菜作りは土づくりから」という話をしています。まずは「今日一日、ここの土の石を全部取ろう」というところからスタートするようにしています。土地管理の大切さを知ることは、農家さんへのリスペクトにつながっていくと思うのです。学校での開墾というところから、子どもたちと一緒に学びたいと思っています。例えば、サツマイモ掘りなど、出来上がったものを収穫する機会はあると思うのですが、収穫に至るまでのプロセスを体験する機会はあまりありません。なので畑づくりの段階から、子どもたちと一緒にやろうと考えています。こうした実践をやり易い環境ではないけれど、だからこそ意味があると思って取り組んでいます。
(吉野さん)先ほど、石井さんの事例報告では紹介されませんでしたが、彼は芹沢地区でゴミを拾う、クリーンナップをグループでやっています。野菜を育てるだけじゃなくて、環境を再生する活動も続けている。そういう地道な活動は、素晴らしいと思うのです。石井さんに、その活動に参加してくれる人をどういう形で呼びかけているのか、お尋ねします。
(石井さん)ふるさとファーマーズの広報は、今はSNSが中心となっています。SNSを通じて、小さな子どもを持つお母さんの関心が高いというイメージを持っています。もう一つは、オーガニックとか環境再生する畑について、もっと多くの人に知っていただきたいので、メディア関係者にも積極的にお話を行っています。
2024年と2023年の11月3日に、ハーベストパークというイベントを開催しました。15,000人ぐらい参加する大きなイベントになったのですが、その発端となったのが里山クリーンの活動です。茅ヶ崎の南側にお住まいの方には想像ができないかもしれないですが、市の北側では不法投棄がすごく多いのです。一番ひどい時には、トラック4台分の石膏ボードが捨てられていたり、洗濯機があったり、大きなタイヤが何個も捨てられていたり。そうやって農地を守っていかないと、結局環境が壊れることにも繋がっているのです。なので、そういう状況を出張授業の中でも話すようにしていますし、畑に来た方たちには「農」を守るということは自分たちの環境を守ることだと話をしています。海岸地域でも、一生懸命にビーチクリーン活動をやっていますが、「ビーチに流れていくゴミは、里山や陸地から出てくるものだから、ここも改善していかないといけない。まずは、ゴミを出す人を減らしていかないと。」と言っています。今では、このイベントが周知されてきて、大体30人から50人ぐらいで月1回、里山クリーンをしています。それ以外では、市の「広報シティプロモーション課」や「ちがすき」「タウンニュース」に活動をPRし、広報協力していただいています。
(吉野さん)オーガニッカーちがさきでは、援農情報を一枚のチラシにまとめています。先ほど、私の方からぜひ土に触れるといいですよとお勧めしましたけれども、そのための入口は色々とあります。このチラシの中には、12の有機農家さん情報がありますが、皆さん、それぞれに窓口を開いてくださっているので、そういうところに問い合わせるといいと思います。農家一覧の中で、実際に家を継いで農家をしているのは1軒だけです。それ以外は、広告代理店やIT関係の仕事、教職の仕事など、前職はバラバラで、そういう異なる背景が、持ち味になっています。ふるさとファーマーズの石井さんも、以前は不動産業界にいて、今はコンクリートを剥がす側になっています。そういう目線を持っている人たちが、農に加わることで、より豊かな活動につながっていくと思っています。石井さん、どう思いますか?
(石井さん)僕も「農業は本当に思っている以上に大変でもあり、すごく楽しさもある」と感じています。僕が100回こうしてお話するよりも、1回援農に来ていただく方が、よっぽど農の本質的な理解につながると思うのです。収穫でも種まきでもいいですけど、一歩入ると、知らないことがたくさん見えてくるのです。収穫をすると、「その前のプロセスはどうなっているのだろう?」と。そうして、どんどん深掘りしていくと、1年間畑をやりたくなっていきます。この場に来てくださっている方は農に関心があると思うので、まずは収穫だけでも種まきだけでもいいです。そういったことが広がっていくと、農業の問題は、自分ごとにできると思うのです。農業は、ガス・電気・水道と同じぐらい大事なインフラだと思います。僕も、吉野さんの「土に触れてほしい」という切な願いと同じ気持ちを持っています。
グループワーク~全体会
農業に関心のある市民・農家・自治体職員・会社員など様々な立場の参加者が、グループに分かれて情報交換をしました。
終了後のアンケートでは、
「不耕起栽培について知ることができた。」
「小学校給食や、援農など、地域とのつながりの話が良かった。」
「ファーマーズ・ファーストという言葉を知れてよかった。」
・・・などの感想をいただきました。