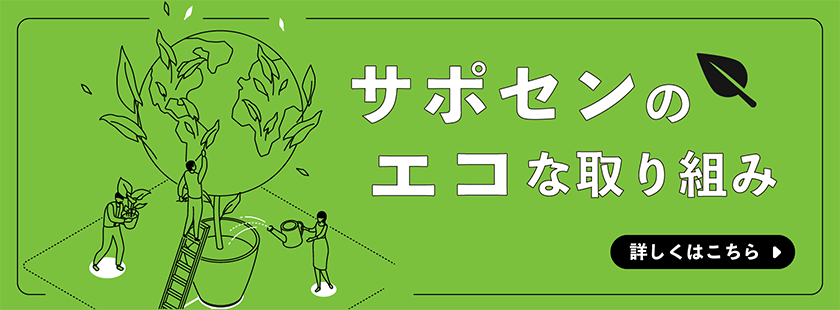【開催報告】第2回 茅ヶ崎ミライトーク ~5年・10年先のまちの未来を想い描いてみよう
NPO講座4
「第2回 茅ヶ崎ミライトーク」
「市長・副市長と市民活動団体が、5年後・10年後の輝く未来に向けて、まちづくりへの思いを語り合う未来志向の対話イベント」の第2回を開催しました。

日 時:2025年2月22日(日) 14:00~16:00
会 場:ちがさき市民活動サポートセンター フリースペース大
参加者:52名(行政、団体、サポセン含む)
≪プログラム≫
(1)「市民活動団体と行政との協働~みんなで取り組むまちづくり」ミニレクチャー
(講師:市民自治推進課 協働推進担当 柿澤良昭さん)
(2) 事前申込5団体による5分間プレゼン
活動紹介、「市と連携したいこと、一緒に取り組みたい事業」の提案
塩崎副市長、竹内教育長から各団体へのひとことコメント
(3) 第1回ミライトーク プレゼン参加団体からの進捗報告
「市民参加型のデジタル化推進活動」
(発表者:ちがさきデジタル活動推進連絡会/NPO法人セカンドワーク協会 四條邦夫さん)
(4) プレゼン団体の感想共有と一般参加者質疑応答
(5) 寺島くらし安心部長、佐藤市長からの応援メッセージ
市民活動団体と行政との協働
~みんなで取り組むまちづくり

これまで実施された様々な分野での協働・連携事業から事例紹介がありました。また、協働の形態や市が事業を行うときのルールや考え方、これから行政とともに事業に取り組みたいと検討する場合、どのようなアクションを起こしてどんな風に進めていくとよいか等、行政の視点からわかり易くお話をしていただきました。
団体プレゼンテーション ~発表テーマ、内容~
1. C3(シースリー)大作戦
「茅ヶ崎発の小さい段ボールコンポスト容器C(チー)ポスで、生ごみを堆肥として活用し、循環型社会に貢献したい」

段ボールコンポストとは、好気性微生物の強い分解力で生ごみを堆肥に変える容器のこと。
「燃えるごみの袋サイズを半分にできる、出来た堆肥を家庭菜園に使える、微生物を身近に感じ学びがあるので子どもの教育にもよい」等メリットがある。
SDGsで持続可能な社会を作ろうと5年前から段ボールコンポストを始めたものの、挑戦と失敗の繰り返し。「においや虫、混ぜるのが大変、段ボールが濡れて壊れる、コストがかかる」等の課題にひとつずつ対策を施し、ようやくストレスなく取り組めるコンポスト容器が出来上がった。

現在YouTubeで情報発信をしている。今後は地域や小学校でコンポスト教室を行うとともに公式LINEを活用して取り組まれる方への支援やフォローをしていきたい。また、放置竹の資材活用、畑や家庭菜園で活用してもらえるよう、個人の方や団体へ働きかけをしていきたい。市とも連携しながら循環型社会の形成に貢献していきたい。
◆ ◆ ◆
2. 一般社団法人 湘南サドベリースクール
「『公教育に合わない子ども、多様な学び場で学びたい子どもの権利を共に守っていきたい』1.各家庭への経済的支援 2.情報共有の場作り」

十間坂にある古民家で、オルタナティブ教育のひとつ「サドベリー教育」を実践している。
2008年に任意団体として開校、2016年に一般社団法人化した。年齢ミックスで、誰でも対等に民主的に話し合い、学校のルールや時間、予算など他では大人だけで決めるようなことも、大人と子どもが対応に話し合い責任を持って決めている。
今、不登校状態の子どもが増えており様々な支援の取り組みがあるが、一方的に学校復帰、公教育に戻すのではなく、子どもの声を聞きながら多様な学び場、やり方で学びたい子どもの権利を守っていくことが大切。そのためにも他の自治体で実施されているフリースクール等補助・助成制度があるとよい。
また子どもが主体的に自分の教育、学び場を選べるようにするための情報共有の場づくりを市内の教育関係者や保護者、子どもたちと連携して作っていきたい。大人だけで進めずに子どもが参加できる扉が開かれていることが必要。子どもも大人も対等に尊重しあい、一緒に学びの権利保障を進めていきたい。
◆ ◆ ◆
3. 一般社団法人 遊びでまちづくりする準備室
「『まち全体が学校』地域の人材と学校教育をつなぐデジタルプラットフォーム、マッチングで子どもたちに豊かな学びを!」

「まち全体が遊び場・学び場」をコンセプトに青少年の個人の「生きづらさ」の解消と地域の関係性の希薄さの改善をテーマに活動。
「まちのスコーレ」プロジェクトでは、子どもたちが家庭や学校以外に地域の多様な他者とつながる機会を、様々な人たち・団体と協働で創っている。地域の居場所が増えることで「自分の世界はもっと広いかもしれない」という気持ちを抱くことができる。
自分探求、自己実現できるきっかけを創りたい。今の社会は、少し前までは家庭や地域で行っていた生活面・文化面の体験を学校に求めすぎているのではないかと感じる。渋谷区の小中学校では2024年度から、午後は「探求」の時間としてNPOや個人、企業が総合学習を支援している。
学校と地域の連携を茅ヶ崎で進めるにあたって、学校ニーズと多様な地域人財とのマッチングポータルを提案したい。熱意ある先生やコーディネーターに依存しないサスティナブルな仕組みの構築ができればと考えている。子どもたちに豊かな学びを届けていきたい。
◆ ◆ ◆
4. ARTノTANEMAKi(あーとのたねまき)
「クリエイティブ・センター設立~子どものクリエイティビティを中心に、モノやコト、クリエーター、親、はたらく人、茅ヶ崎市民の誰もが集まり、学ぶことができる場をつくります」

企業のものづくりの過程で不要になった素材を、安全性と審美性を吟味したうえで活用し、子どもたちの創造活動の場をつくっている。
今回提案する「クリエイティブ・センター」では、子どもが常にクリエイトする楽しさを体感できる場づくりに加え、子どものクリエイティビティに関わる大人の育成や教育と産業・行政との連携、コミュニティネットワークづくり、子ども発信の「やりたい!」から始まるプロジェクトを支える仕組みづくり等を行う。
海外では、イタリアのレッジョ・エミリア市やボローニャ市、ニューヨーク市、ストックホルム市などが教育行政産業や市民と連携をして運営をしているが、日本に市営のセンターはない。クリエイティブな学びは学力・人間力を高めると言われている。学校以外の多様な居場所づくり、「クリエイターシティ・チガサキ」としてクリエイティブな文化の醸成、地場産業と繋がり教育に還元できる仕組みづくりなどにも貢献できる、文化拠点となる場所を市と連携して作っていきたい。
◆ ◆ ◆
5. 未来を考える市民の会
「市議会傍聴ツアー:わたしたちの暮らしにかかわる市議会の情報共有や学習会など市政のまなび場づくり」

政治に興味を持った時に、議員や行政への不満や批判は聞こえてくるが、学べる場が見つからなかったことから現場を見に行くツアーを2018年から企画。
毎回3~5名の方に参加いただいている。初めて傍聴する方も多く、興味を持ってもらえるようツアー広告風に配付資料を作成。始まる前に、議会の流れや議員が座る位置、その日の議題や議案の内容など傍聴ポイントについても説明を行っている。終了後には傍聴レポートをSNSで公開している。
その他にも一緒に議会映像を観たり議員との対話企画、ツアー参加者からのリクエストでテーマを絞った勉強会なども実施している。茅ヶ崎市議会は氏名と住所の記名が不要、撮影や録音可、資料が公開されている他、車いすの方や子ども連れでも傍聴しやすい環境だと思うが、参加が少ないのが非常にもったいない。
議場に入るとおしゃべりができず、その場でわからないことを解説してほしいという要望もあるので、「特別傍聴室」を使えるとありがたい。
◆ ◆ ◆
プレゼン団体へ統括コメント~行政より

子育て中の世代による、子どもの教育をテーマとした内容が多く、今回急遽参加してくださった教育長からは「これからの社会を作って生きていく主人公である子どもたちが、自分たちの学びを自分たちでデザインしていけるように、これまでの常識に囚われない豊かな発想で、多様な学びの場、地域とのつながりをつくることが大事」と、学校現場も同じ思いであるとのコメントをいただきました。
第1回プレゼン参加団体から進捗報告
ちがさきデジタル活動推進連絡会/NPO法人セカンドワーク協会
特定非営利活動法人パソコンボランティア湘南とともに連絡会を立ち上げ、誰も取り残さないデジタル社会の実現を目指して定期的に意見交換をしている。
行政の担当課とも打合せをして、スモールスタートで成功体験を積んでいくこととなった。まずは、まちぢから協議会連絡会のWEBサイトリニューアル支援や、市民のよりよい暮らしに役立つデジタル講座を開催していく予定だ。自分たちにできる「現場で起きている課題やニーズなど『市民の生の声』を、行政に届ける」役割を果たしていきたい。
社会課題解決・社会貢献のための地道な市⺠活動は、とても⼤事なこと。行政へのアピールの機会やサポセンを積極的に活用してほしい。また他の市⺠活動団体等との連携は、⾮常に学びが多い。今後も、市民が地域で活躍できる機会づくりと、この取り組み(ミライトーク)の継続をぜひお願いしたい。
市民活動団体の発表終了後には、それぞれの団体から感想をいただき、一般参加者からも活動の苦労や未来へ託す思い、子育ての悩みなどが語られました。
最後に、くらし安心部寺島部長からは「様々な連携・協力の可能性があることがわかった。市民活動団体の皆様と職員との顔の見える関係性づくりを進めて、連携・協力に向けた土壌を作っていきたい」との心強いメッセージをいただきました。
そして、佐藤市長からは「(一週間の歌のように)月曜日から毎日、日替わりで今日の発表団体の活動に参加できるね」と、ユーモアも交えて感想をいただきました。また、ご自身の議員時代の経験事例をもとに「できないできないではなくて、どうすればできるかっていうことを、市職員と市民活動団体の皆さんと一緒にこれから考えていきたい」と熱く語ってくださいました。

前回に引続き、終了後には名刺交換をしながらの交流が続き、参加者一同が「協働のまちづくり」への思いをしっかりと共有できたイベントとなりました。
【参加者アンケートより(一部抜粋)】
・「茅ヶ崎をよくしたい」と思っている団体の活動や思いを聞くことができてとても良かった。
・各団体のプレゼン後に、その内容について質疑応答や意見交換をする時間があった方がよかったと思う。
・取り組みの目的や戦略など、より具体的に考える良い機会になった。プレゼンに対する質問がたくさんあると嬉しい。
・小さな取組みから大きな未来へと、つながっていくという風に感じた。
・どの団体のお話も興味深く、もっともっと伺いたいと思った。このような場も、人と人がつながる場なのだなと感じる。前回も参加させていただいたが、どの活動の中にも子どもの学びや成長に関するものがあり、これから最も大切で急ぐべき課題は、どの子どももその子らしく成長していけるための支援だと感じた。子どものいる場所って、優しく温かくなりますね。
・教育長の学校以外にも、あらゆる所に学びがあるという発言を聞いて良かった。行政だからできること、市民だからできること、それぞれを持ち寄ってより楽しくハッピーな茅ヶ崎になったらいいなと思う。
・学校教育、社会教育のことを、市民レベルで話し合いたい(市長のおっしゃった「ひざつき合わせて」一緒に考えたい)
・この企画はとても良いと思う。第3回も是非よろしくお願いします。
・他団体や市職員の方々とお話ができてよかった!
・地域活動はサークル活動のイメージが強かったけど、茅ヶ崎の団体さんは地域課題解決型の、とても感度が高いことを知った。市と団体が一緒に意見を言い合うこの場がステキ。
・5年ぐらいかけて計画を進めて良いのだということが分かった。まずは団体として仲間を募らないといけない。相談窓口があることも分かり、少し前に勧めそうな気がした。名刺も作ろうかと思った。
・行政側と市民側と、お互いに協働していきたいという熱気と、ポジティブな空気がとてもよかった。何かしら、小さな実でも結んでいけたらいいと思った。
・ミライトークを踏まえて、市の中でどのくらい議論が続いているのか可視化して、一時的な盛り上がりで終わらないといいなと思う。ミライトークの広報を市にももっと協力してもらい、大きな場所でたくさんの人に参加してもらいたい。職員の方にも是非参加してもらいたい。
・ミライトークからさらに発展して、各団体の活動と行政の施策や計画を結びつけていく場を、サポセンなどで設けていただけたらありがたい。
2023年度に開催した「第1回 茅ヶ崎ミライトーク」の催報告は コチラ よりご覧いただけます。